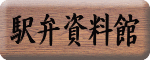











旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。
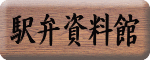














高千穂町は、宮崎県の北端で九州山地の中に位置する、人口約1万人の門前町(鳥居前町)。日本の神話で天孫降臨の地とされる、有史以前からの伝承に基づく観光地。大正時代までに熊本と延岡を結ぶ鉄道が計画され、1972(昭和47)年7月に高千穂へ達したが、全通することなく豪雨災害で2005(平成17)年9月に不通となり、そのまま廃止された。廃線跡の一部で2010(平成22)年4月からカートが運行され、高千穂駅の駅舎や構内が使用される。駅弁は2003(平成15)年10月にトロッコ列車の乗客向けに発売されたが、鉄道の休廃止とともに消えた。1972(昭和47)年7月22日開業、2008(平成20)年12月28日廃止、宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井。
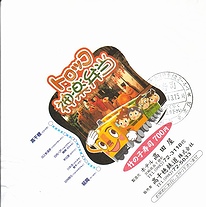

2003(平成15)年3月に登場の高千穂鉄道トロッコ列車を記念し、同年10月1日に発売したと思われる、高千穂鉄道史上初の駅弁。但し乗車3日前までに弁当を注文したトロッコ列車の利用者にのみ発売されるそうで、実態は駅弁ではなく車内弁当。同年9月10〜16日の日本橋高島屋の宮崎物産展で先行販売された
竹の輪切りをそのまま駅弁容器にして、竹皮をかけて輪ゴムでしばり掛紙をかける姿は見ただけで雰囲気を盛り上げる。中身は竹の子を巻いた寿司が二個に延岡特産めひかりの唐揚げ、椎茸や人参等の大粒な煮物などで、容器と敷かれた笹の葉の香りに包まれて味覚嗅覚触覚に訴える。名駅弁となり得る実力を感じた。掛紙によるとホテルが製造し鉄道会社が販売する。
高千穂鉄道は宮崎県の延岡と高千穂を結ぶローカル線で、1980(昭和55)年の国鉄再建法により廃止対象線とされた高千穂線を、第3セクターの鉄道会社が1989(平成元)年に引き継いだもの。そのトロッコ列車とは、日本宝くじ協会の助成で2両の車両を導入して2003(平成15)年3月21日に運行を開始した、延岡・高千穂間の観光列車。
しかし高千穂鉄道は2005(平成17)年9月5日の台風14号に伴う豪雨で多くの鉄橋や線路が流失、直ちに全線が不通となった。復旧費用が出せないことから同年12月には廃線を決定、2009(平成21)年3月までに法的な手続きをすべて終えた。トロッコ列車の運行も当然に終了し、この駅弁も現在は販売されていないものと思われる。
被害が少ない区間での運行再開の動きは、2010年代にも何度か新聞報道がなされたが、それもいつしか消えた。まだ新しかったトロッコ車両2両はJR九州に売却され、改装のうえ日南線の観光特急「海幸山幸」に転用、普通車両のうち1両は徳島県の阿佐海岸鉄道へ移籍し、いずれも高千穂では見えなかった海を見ながら走った。2010年からは高千穂駅付近の線路と、自動車を改造した車両を使い、「グランドスーパーカート」として体験乗車できるようになっている。駅弁は復活していない。
※2023年2月補訂:現況を追記