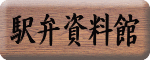











旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。
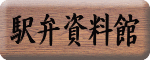













2025(令和7)年1月の京王百貨店の駅弁大会で実演販売。続いて熊本の鶴屋、仙台の藤崎、博多阪急の駅弁大会でも実演販売。これらの催事の合間に能登中島駅での予約販売を実施し、以後も週末の営業を続ける模様。これらの催事では、2024年1月の地震と9月の豪雨で被災した能登の支援や復興の意味を持たせ、能登半島のローカル線の駅で売られていた駅弁として実演販売し、その話題はこのとおりメディアで発信された。
底やふたが上げられていない、小柄な正方形のプラ容器に、金沢醤油の茶飯を詰め、能登かきのうま煮、かきのだしで炊いたごぼう煮、煮汁を混ぜた玉子焼、五郎島金時のレモン煮、能登野菜中島菜漬けで覆う。他駅のカキ駅弁より量が少なく値段が高い、感覚的に1.5倍の値段が付いたと思えるが、小粒が特徴の能登かきを含め地元の食材で固めた内容は大量や安価に向かないだろうし、報道ではカキの仕入れ値を抑えて二千円を切る価格にできたと紹介された。
能登中島駅は、古くは鉄道省、国鉄、JRの七尾線、1991年からのと鉄道の、七尾や和倉温泉と穴水や能登の間にある駅。2004年に七尾市へ合併されるまで町制を敷いた石川県鹿島郡中島町の玄関口で、かつて普通列車が折り返したり、急行列車のごく一部が停車したことはあるが、主要駅でも列車運行の拠点でもない駅で、駅弁もなかった。2004年に昭和時代の郵便客車「オユ10」の保存場所となり、2017年に鉄道会社の駅売店ができ、路線長で営業規模を7割も縮小したのと鉄道の主要駅として、観光客が立ち寄るようになってきた。
この売店を2019年に引き継いだ、地元のテント製造卸業者の夫妻が、調理場を設けて惣菜を売り始め、コロナ禍による休止を経て2023年3月には弁当も売り始めたという。これは「能登のかきめし」でなく、駅弁として紹介されることもなかった。地震による再度の休止を経て、報道によると福井県の催事業者の提案により、この駅弁を駅弁大会で売り出した。だから能登地震からの駅弁復活という各所での紹介は間違いだと思う。それでも駅弁大会で生まれ地元に来た駅弁、例えば京王百貨店の駅弁大会では摩周駅「摩周の豚丼」のようなことが、またあってよい。弁当の現物に示されない調製元は「わんだらぁず」。