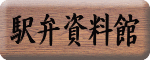











旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。
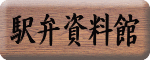













五島列島などへの船便が発着する長崎港の、ターミナルビルの売店で売られていたお弁当。電子レンジ対応の白い容器に、白御飯、ハンバーグ、鶏唐揚、目玉焼き、千切りキャベツ、福神漬を詰めたお惣菜。ハワイの丼ものの名前が付いているが、内容からして関係なさそう。JR長崎駅の駅弁屋の調製であったため、買って船内で食べてみたが、長崎や駅弁の味はしなかった。この売店に、駅弁や空弁や港弁らしきものはなかった。
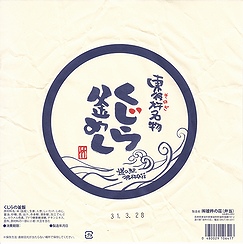

長崎県東彼杵郡東彼杵町の大村湾沿いにある、国道205号に面した道の駅「彼杵の荘(そのぎのしょう)」で、2012(平成24)年9月に発売。駅弁でも使われるプラ製の釜型容器には、ちゃんと専用の掛紙がかけられている。この容器に炊込飯を詰め、炒り卵で覆い、クジラの本皮湯かけと赤肉を少々散らし、シメジと紅生姜と茶葉を添えたもの。淡く美味で、臭みは皆無で、なにより安価で、こういうものが駅弁や空弁になっていれば、もっと注目されるかと。
現在の長崎県では江戸時代に、沿岸や五島列島や壱岐・対馬で捕鯨が行われており、現在の東彼杵に水揚げされて流通したそうな。そのため東彼杵には今もクジラ屋が多く、道の駅でもクジラ肉が販売されていて、こんな道の駅弁が誕生している。
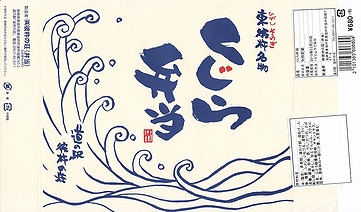

長崎県東彼杵郡東彼杵町の大村湾沿いにある、国道205号に面した道の駅「彼杵の荘(そのぎのしょう)」で、以前から販売されているお弁当。駅弁でも使われるような黒い容器には、ちゃんと専用の掛紙がかけられている。この容器に炊込飯を詰め、炒り卵で覆い、クジラの本皮湯かけを散らし、クジラ竜田揚、ふろふき大根、たくあんを添えたもの。淡く美味で、臭みは皆無で、こういうものが駅弁や空弁になっていれば、もっと注目されるかと。
この道の駅の近くには、JR大村線が通る。1934(昭和9)年12月に長崎本線の肥前山口駅と諫早駅までの区間が短絡されるまでは、こちらが長崎本線であり、門司駅や博多駅と長崎駅を結ぶ列車が経由した。しかし起終点の早岐駅と諫早駅を除き、駅弁が売られたという話を聞いたことがなく、その両端駅も今は駅弁がない。こうやって弁当にできる名物はあるので、新幹線が新大村駅や諫早駅に来る頃には何かできるだろうか。



諫早駅から大村線で約10分。大村市は長崎県の県央で大村湾に面した、人口約10万人の城下町。戦国時代から大村氏大村藩玖島城の藩政が敷かれ、明治時代に陸軍の駐屯や海軍航空廠の設置で栄え、第二次大戦後は宅地や高速道路や世界初の海上空港が立地した。駅弁はないが、第二次大戦前の構内営業者や第二次大戦後の鉄道弘済会が弁当を販売したかどうか。1898(明治31)年1月20日開業、長崎県大村市東本町。